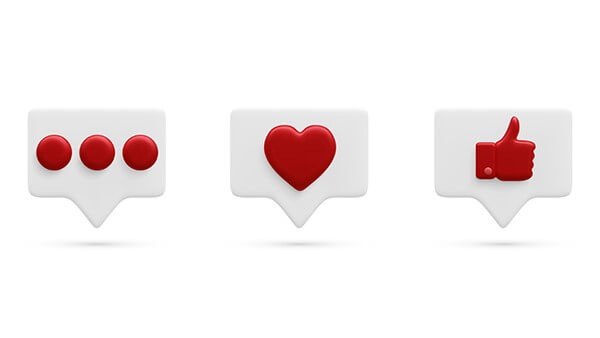2026年の変化に備える!注目すべきデジタルマーケティングトレンド

2025年、デジタルマーケティングの世界ではAIの進化やプライバシー規制の強化、検索体験の再構築など、あらゆる領域で急速な転換が加速しました。
2026年は、その延長線上で、業界構造やマーケティング手法が再定義されるタイミングを迎えます。クリック数やインプレッション数だけを追う時代ではなく、これからは「真のエンゲージメント」をどう築くかが問われています。
AIの進化・浸透、ステーブルコインの普及、新しい決済手段の拡大、そしてグローバル経済の再編。こうした外的要因も相まって、2026年はビジネスの“再設計”が求められる年となるのではないでしょうか。
今回は、そんな激動の年に備えるために、グローバルマーケターが押さえておきたい「2026年の主要なデジタルトレンド」をご紹介します。
目 次
2026年、注目すべき主要デジタルトレンド
1. AI主導のマーケティング時代が本格的に到来!
最近まで、人間の専門領域だった、クリエイティブ制作も、AIが高速かつ精度高く補完するようになりました。AIが画像や広告コピーを自動生成し、ユーザーの行動データに基づいてリアルタイムで最適化を行う時代です。動的なウェブサイトコンテンツやレコメンデーションから、キャンペーンワークフローまでAIを活用してパーソナライズする時代はもう目前に迫っています。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、「Metaは2026年までには、AIを活用した広告自動化を目指している」と報じられています。これは、広告主が製品画像と予算を入力するだけで、AIが画像・動画・テキストを含む広告全体を自動生成し、最適なターゲティングや予算配分の提案までを自動で行うというものです。
まだ試験段階ではあるものの、このような変化は、単なる業務効率化に留まらず、マーケティングそのものを“再定義”する動きと言えるかもしれません。
AIは「人間に代わる存在」ではなく、「人間の創造性を拡張する存在」として進化しています。同時に、AIをどのように活用し、どこまで人が関与するかという判断も重要です。
マーケターの役割は「手を動かす人」から「戦略と創造性を導く人」という視点で、マーケティング業務を再定義しましょう。AIを使いこなす力こそが、これからのブランドの競争力を左右する時代が始まっています。
2. SEO×GEO×AEOのトリプル最適化 😿
ユーザーの検索の主戦場はGoogle検索から、ChatGPT、Gemini、Perplexityなどの会話型AIエージェントに移行しつつあります。
こうしたAIエージェントの台頭により、ユーザーは「検索する」から「答えを得る」へと変化しています。
この流れにより、従来のSEO(検索エンジン最適化)に加えて、AI時代に適応した新しい最適化が求められています。具体的には、ユーザーが検索せずに回答を得る「ゼロクリック検索」への対策(AEO)や、AIの回答に引用されるコンテンツ作り(GEO)が重要になります。
つまり今後は、SEOを再考し、AEOとGEO対策を講じるトリプル最適化戦略がデジタル戦略の中核になるでしょう。
![]() 対策:
対策:
| GEO(生成エンジン最適化) |
| 目的:AIがコンテンツを参照・引用する「知識源」として選ばれること 対策:E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の徹底強化、構造化データの活用、サイテーションや被リンクの獲得など 注意:トラフィックが獲得できるか不明 |
| AEO(回答エンジン最適化) |
| 目的:ユーザーの質問に対して一文で答えを提示できる構成・内容であること 対策: E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の徹底強化、FAQ形式のコンテンツ、構造化データの活用、サイテーションや被リンクの獲得など、簡潔な見出しと段落構成など 注意: 遷移先として表示され、トラフック獲得の可能性あり |
| SEO(検索エンジン最適化) |
| 直近の動き:Googleの2024年3月のスパムアップデートとコアアップデートでは、低品質な大量生産コンテンツに対して積極的な排除が講じられている。今後は、データに裏付けられた独自性・専門性・体験価値を持つコンテンツだけが上位表示される傾向が強まると予想されている。 対策:信頼性の高いコンテンツ作りは、必須 |
3.データプライバシーの管理と規制強化
Cookie規制やプライバシーサンドボックスの進展により、ファーストパーティデータの活用がより重要になります。また、AIを活用した顧客管理などは、扱うデータの機密性も高まります。
顧客の同意を前提としたデータ収集、データの匿名化、サーバーサイド計測の導入など、企業には「データの透明性と信頼性」が問われる時代です。変化する規制を常に把握し、プライバシーに配慮しつつ、ユーザー体験を損なわないマーケティング戦略が求められます。
規制は今後も国や地域を超えて厳格化されるとみられており、マーケティング戦略にプライバシーを軽視する企業は、罰金だけでなく、ブランド価値という大きな資産を失うことになるでしょう。
4.ソーシャルコマースの常態化 
SNSでの“発見”と“購入”の境界は、世界的に急速に薄れています。
特に東南アジアでは、TikTok Shop や Instagram Shopping など、アプリ内で完結する購買行動が爆発的に拡大中です。インターネット・スマートフォンの普及率が高いこの地域では、SNSが日常生活の一部として浸透しており、実際に「SNS経由で商品を購入したことがある」と答えた割合は、インドネシアで69%、フィリピンで73%と、世界平均の46%を大きく上回っています。
さらに、アジア太平洋地域では「デジタル経済枠組み協定(DEFA)」の推進により、デジタル貿易や越境ECの整備が進み、オンラインからオフラインへの購買の流れが一層加速しています(World Economic Forum)。これにより、ソーシャルプラットフォーム上の購買体験は、国境を越えた販売チャネルとして定着していくでしょう。
一方で、ソーシャルコマースの潮流は東南アジアにとどまらず、グローバル規模へ広がっています。TikTok Shopは欧州や中南米など新たな市場へ積極的に進出し、米国では前年比3桁以上の売上成長を達成しました。今後は日本を含む、さらに多くの国・地域への展開と物流パートナーとのの連携を強化するとみられています。
さらに、WhatsAppも「チャット上でそのまま支払い・購入が簡潔できる仕組みが導入されつつあり、一部の国では、会話から決済までをシームレスに行えるようになっており、ブランドと商品者のコミュニケーション体験は次の段階へと進化しています。
ソーシャルメディアが「広告の場」ではなく「販売チャネル」です。ブランドはインフルエンサーとの協業やライブ配信を通じて、より自然で信頼感のある購買戦略の構築が求められます。
5.「情報の信頼」をめぐる新時代
近年、SNSのダークソーシャル化(クローズドな共有)、プライベートコミュニティの拡大、そしてAIによるパーソナライズ回答の普及により、私たちの情報環境はこれまでになく細分化しています。
人々はそれぞれ異なる情報空間で生活し、フォローするインフルエンサーも、信頼する情報源も、受け取るAIの回答すらも異なります。
こうした“情報の断片化”が進む中で、企業に求められるのは、複数のコミュニティにまたがって存在感と信頼を築きつつ、どのチャネルでも一貫したブランド像を保つことです。
一方で、AIが生成するコンテンツが日常化した今、「人間が作ったもの」と「AIが作ったもの」の境界はますます曖昧になっています。近い将来、製品紹介動画や広告の中で登場する人物が、実在の人なのかAIアバターなのかを見分けることが難しくなるでしょう。
このような時代に、消費者が求めるものは、“完璧な映像”よりも“本物らしさ”です。若者世代、特にZ世代を中心に、飾らない表現や舞台裏のリアルな姿に共感する傾向が強まっています。
情報があふれ、誤情報も巧妙化する中で、ブランドの信頼性こそが最大の差別化要因になっています。注目を集めることよりも、「どれだけ信頼されるか」が問われる時代です。
AIによる引用、コミュニティでの推奨、ブランドの一貫性、データ利用の透明性といった”信頼指標”が、今後の評価基準となるでしょう。
6.音声・ビジュアル・マルチモーダル検索が主流に
キーワードを入力して、情報を探す――そんな検索は過去のものになりつつあります。
いまやユーザーは「声」や「画像」、あるいはその両方を使って検索する時代です。例えば、“この靴に似たデザインを探して”と話しかけながら写真をアップロードする。AIは音声・画像・テキストを同時に解析し、ユーザーの意図を読み取って最適な結果を返します。これが、急速に普及しつつある「マルチモーダル検索」です。
GoogleのLens、PinterestのVisual Search、そしてYouTubeやInstagramでの「音声×画僧×テキスト」を統合したマルチモーダル検索技術の開発が進んでおり、検索は「入力」ではなく「会話」へと進化し始めています。
AIがこうした複数の情報モードを統合的に理解することで、ユーザーの行動はより直感的かつ自然になっていくでしょう。
――Appleが変える”検索”の概念 ![]()
2025年、Appleが発表した Apple Intelligence は、この流れをさらに加速させました。
Siriが大型言語モデル(LLM)をネイティブに統合したことで、ユーザーは Safari を開くことなく、質問をすれば即座に答えが返ってくるようになりました。Appleの新しいデバイスでは、カメラ・音声・テキスト入力が完全に連動しており、「話しかけながら撮影する検索体験」が一般化しています。
この変化は、企業のコンテンツ戦略にも大きな再設計を迫ります。テキストだけを最適化しても、AIアシスタントや音声検索では十分に理解されません。
今後は以下のような観点で、コンテンツを構築する必要があります。
- 会話調・質問形式の構成で、音声でも自然に聞き取れる文章を意識する
- FAQやHow-to形式で明確に質問に答える構造を整える
さいごに
2026年のデジタルマーケティングトレンドは、未来予測ではなくすでに始まっている変化の延長線上にあります。AIの進化は止められませんが、それをどう使うかは人間次第です。
「短期的な利益最大化」を優先するのではなく、本質的な価値を見据え、創造性を高めるためのAI活用、信頼構築、そして人間らしさを保つブランド戦略を実現できる企業こそが、次の時代を導いていくのかもしれません。
2026年は、AIやテクノロジーによって、富や情報、機会が再び分配され、人と企業、そして世界の関係がリセットされつつあるのかもしれません。今後、デジタルの激変は止まりません。だからこそ、私たちマーケターは“変化を恐れず、進化を楽しむ”姿勢で前へ進んでいきたいですね。

吉田 真帆 マーケティング部 プランナー
iCJの自社マーケティングを担当。オーストラリアの永住権を取得したにも関わらず、思いもよらず日本に帰国。 オーストラリア→カンボジア→日本→シンガポール→2025年末~日本